| 雑 記 |
| 他の頁に収め難かったものを集めています。 |
| 正しい空気圧 | ||||
|
|||||||||||||||
| 自転車探検! https://jitetan.com より | |||||||||||||||
|
なるほど、そうだったんですか。
Type-R(BIG APPLE)の空気圧は体感で決めていましたから、一度きちんと測ってみましょう。 ・ ・ ・ 私の場合は現状のままで問題なさそうです。 リヤは乗り心地が損なわれない=350kPa、フロントはコーナリングで腰が砕けない=250kPa、です。 フロントはとにかく荷重が小さいために、静的な計測をしてもたいして変位が出てきませんから、 適当に空気が入っていればいいということになります。 |
|
| 英式バルブのタイヤの空気圧管理 | ||||
|
基本的に正確な空気圧管理は無理ですから、スーパーバルブに交換するのが早道なのですが、
今や品質管理が相当にお粗末らしく、虫ゴムの方が信頼性が高いという評価が優勢な状況となっています。 では、無印良品16型のような英式バルブの場合、どうやって空気圧を合わせればよいのでしょうか? |
|||||||
|
|||||||
|
最後のやつは米式と英式に、同じ回数ポンピングした際の差異だそうで、誤差は 15% に留まりますが、 他の2者は 40% 以上となります。 趨勢としてはこちらでしょうか。 最初のサイトは、現場感覚に満ちていますし、 2番目のサイトは、論理的展開で私のポンコツ頭では理解するのも大変な情報量で、 130kPa の情報源に到達する前に離脱してしまいました。 残念ながら、歳には勝てぬ、ってやつですね。 最後のサイトは、そんな方法でいいのか心配になりますが、私の感覚には最も近いです。 状況・条件の仔細にも依るのでしょうが、さて。 |
|||||||
|
私個人としては、ゆっくりポンピングすれば目安となる値は取れますので、それで十分管理できると思います。
ポンプのハンドルをグッと押して「プシュッ」、ではなく、 「プっ・シュ〜〜〜」とゆっくり定圧送りする際の、落ち着いたメーター値を読み取ります。 (私は、米式、仏式でもそうしていますが) ただ、虫ゴムがへたっているとダメみたいですし、 200kPa程度に空気が減った状態からでないとうまくいかないのですが、 イメージとしては、虫ゴムに少しだけ開いた隙間からゆっくり流し込む、みたいな感じでしょうか。 真の値ではない感触はありますが、気にするほどの誤差ではないと思います。 この時のタイヤの硬さを覚えておけば何とかなります。 また、適正値も人それぞれですから、経験に基づいた確信があれば、それに従うのが良いと思います。 |
|||||||
 
|
スーパーバルブ 2種です。
30年ほど前に使用したことがありますが、 左側のやつはポンピングの際の抵抗が小さく、 ポンプのメーターで空気圧管理ができました。 右側のやつは虫ゴムよりは持ちが良さそうで 取扱いも楽ですが、それだけ。 今もそうなのかは不明。 |
|
| シングルギアのチェーンの張り | ||||
|
チェーンの張り具合は、中央部の上下振れ幅が 1.5〜2cm というのが通説のようです。
「産業機器用ローラーチェーンにおけるチェーン下側(戻り側)のたるみは 軸間距離の 2% 」に倣って 振れ幅=リアセンター × 4% といったところでしょうか。 チェーンリングの回転角度によってチェーンの張りに強い箇所と弱い箇所が出ますから、 何処で合わせればよいのか分からぬ通説は役に立ちません。 現実には通説の数値がどうであろうと、かなりピンポイントな調整になります。 (張りの不均一に言及した情報は https://www.hozan.co.jp/mechanic/mechanical_advice/chain/page2.html) |
|
| フラットバー | ||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
ツッコミどころもあるような、でもまぁ、世間様の認識としてはそんなところだと思います。
ちょっとスタイリッシュでスポーティで、だから速く走れそう。 ただそれだけです。 あまりに普遍化した、とても分かり易くて今更考える必要も無いようなフラットバーなのですが、 やはりこれ、ハンドルを押さえ込むフォームに適したオフロード専用品です。 基本的に局地戦闘用ですから、疲れます。 戦闘中は分からないだけ。 最後はバーエンドバー等でまともに握らなくて済むようにせねばならぬ、そんな要注意な一品です。 |
|||||||||||
|
オンロードで前傾姿勢の緩いフォームであれば
● 腕を広げ過ぎるとライディングフォームが成立しないので適寸にカット。 ● 幅を詰めるほど手首の角度が自然になり、乗り易くなります。 限度としては、ドロップハンドルと同じ腕の幅まででしょう。 両端クリップオンタイプのグリップを使えば、カットする前に最適なグリップ位置を見つけ易いと思います。 |
|
| DualDriveの回転性能ってどう? | ||||
|
||
|
と、自転車実用便覧という本に書かれているそうです。
一旦権威を認められると版を重ねてもなかなか改訂されずに放置されることもありますから、 提唱されたのがいつごろで、現在にも通用するものなのかどうかが問題です。 それはさておき、文意からすると、やるべきことは調整を追い込むだけしかなさそうですが、 そのあたりも高級品の方がやり易いと聞き及んでおります。 結局、精度の高い高級品の方が性能を引き出し易いということは言えるにしても、 自転車全体に対しては微々たる影響でしかない、ということになります。 あまり深入りしたくない身にとっては「めでたし」なんですが、耐久性については別問題っぽいですね。 そこが高級品が必要かどうかの判断基準になりそうな・・。 DualDrive のようにほったらかしで済む ような気がする やつは、お得なのではないでしょうか。 ホイールの空転時間の長さ自慢動画を見たことがありますが、あれってどうなるんですかね? |
|
| 本家サイト リニューアル 〜 2010/6/26 | ||||
| TYPE FOLDING | TYPE SPORT | TYPE RECUMBENT | TYPE RE | |||
| 謳い文句 | 10年経っても、 あたらしい走行感覚 |
街中での乗りやすさと 使いやすさを極めた、 「最高の街乗り車」 |
世界一乗りやすい、 本格的リカンベント |
世界初の、 電動アシスト装備の 本格的リカンベント |
||
| デザイン したのは |
“景色” と ペダルを漕ぐことの 楽しさ |
“乗り心地” | 日本の伝統建築の 要素を取り入れた 美しいフレーム |
“新しい時代の自動車” | ||
| 車に例えると | オープンカー | SUV | ( 記 載 な し ) | ( 記 載 な し )
(以前は “The MIDSHIP” 出現) |
||
| 販売 | マエストロ店 | (ミズタニ自転車 但し記載なし) | ||||
| Type-F | ||
|
乗ってみないと分からない、筆舌に尽くし難い楽しさがあるそうです。
折り畳み方の動画がありますが、折り畳んだ後の方が問題です。 スペックには “グリップシフター” と記載されていますが、ジュニアの証し レボシフトです。 おそらく最も高額な採用車でしょう。 |
||
| Type-S | ||
|
あらゆる賛美の言葉が使用できるらしい、完全無欠の自転車。 崇拝しましょう。
万能かつ高性能な奇跡の Type-S と、笑える Type-F を2台セットでお買い上げになれば、 さらに完璧です。 |
||
| Type-R | ||
|
とりあえず画像だけ載せておきましたのやる気なし。
マエストロ扱いにならない生い立ちのせいかもしれませんが、あまりの素っ気無さ。 旧サイトでも車体価格の表示が無かったり、妙によそよそしい取扱い様でしたが、 ここに至ってスペックを含めた一切の解説を放棄して、 ミズタニ自転車に倣って本腰を入れて切り捨てにかかった模様。 もはや過去の実績のような扱いである以上、 “E-VEHICLE” ではなく “WORKS” の項に掲載するのが妥当。 捨てられたペットを引き取る里親のような気持ちで購入しましょう。 |
||
| Type-RE | ||
|
こちらももちろんやる気なし。
面倒くさいのか「本格的リカンベント」が Type-R とダブってます。 これはいけません。 電動アシストを付け足した物が「本格的」なわけないでしょう。 もちろん本格的でないものから引き算しても本格的にはなりませんから、 Type-R も本格的なわけがありません。 「電動アシスト付きリカンベント」が “新しい時代の自動車” だというのも滅茶苦茶です。 何でもいいから二代目プリウスのハイブリッドカーブームに便乗してしまえ、という安直なノリ。 「量産車世界初のハイブリッドカー」vs「量産モデル世界初の電動アシストリカンベント」、 字面だけなら似ている部分もありますが、頭の中では絶対に繋がらないでしょう。 普通は。 ミッドシップの件はどうします? |
||
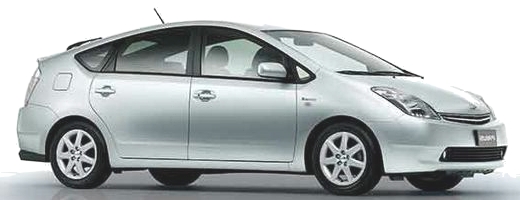 
|
||
| 売れない Type-R | |||
|
Type-F & S の10周年記念限定車の宣伝に押しやられて
Type-R & RE は 生産中止 のような有様ではありませんか。 (お〜こわっ。 冗談にならん) |
|||
| そんなに売れないんでしょうか? | |||
| Type-R を、Tartaruga を初めて検討する方には、どのように映るのでしょうか? | |||
| 実車抜きの外観判断としては | |||
|
● すべて直線基調のデザインに怪しいものを感じる。 背もたれまで平板な直線というのは変だし、伸びた尻尾も要らぬ付け足しに見える。 個性的なデザインだが必然性が疑わしいせいか、個性自体が軽薄そうで、勝負は避けたい。 |
|||
|
● ブランドの信頼度不足
そもそも自転車の専門ではない上に、うわついた表現や変な比喩ばかりを並べ立てられると、 正確な日本語解説能力さえ無いのかと心配になる。 (「一般的」を「本格的」と言い換える神経はパチモノ商売に通ずると判断されかねません) 致命的なのは「たるたる」という音節の繰り返し。 ニャンニャンした言葉でこっ恥ずかしい。 |
|||
| ではフツーな取扱い店で実車を目にしたらどうなんでしょうか? | |||
|
● でかい。 16in.+20in.という小径車なのにフルサイズにでかくて、何処か損をしている気がする。 そんな旨い話があるわけ無いだろう、といういやな予感がする。 |
|||
|
● 本格的にでかいが、ほんとうにどこがどう本格的なのかはよく分からないので、自信が持てない。
店で一番でかい嵩張る自転車を買うことが本当に正しい選択なのか、自信が持てない。 店員の顔に、厄介払いできて喜ぶ表情が透けて見える気がする。 |
|||
|
● 長いキックスタンドが何となく引っかかる。 こういうのも有りなんだろうけれども。
|
|||
|
● しかしけっこう真面目な作りに見える。 ひょっとして大穴ではなかろうか?
|
|||
|
● もう一度Webを検索するが、得るもの無し。
(本家サイトがリニューアルされる以前に、Web上からRの販売情報はほぼ消滅していましたから、 不信感は募ります) |
|||
| ● 他なら何が買えるだろうかと考えているうちに熱が冷める。 | |||
| やはりbikeE型はbikeEでないと無理な気がします。 足せるものは足せばいいんですが、 引くものが少しでもあれば「本格的」には成り立たない気がします。 E-VEHICLE というカテゴリーを創作して立て篭もってますが、購入を検討する方にとっては、 まずは自転車たるリカンベントとしての良し悪しが気になるところでしょう。 「E-VEHICLE」は買った後で入信したら唱えればいいお題目にすぎないのです。 |
|||
| それもそのはず、とっくに生産終了していました 〜 Type-R | ||||
|
情報源は某有名店のブログ (2011/8/10) です。
おそらく上記のサイトリニューアル前にそうなっていたのでしょう。 なるほどね、です。 今となっては “レアモデル” だそうですから、 本家Y氏が嘆いていたように、あまり売れなかったのでしょう。 他のサイトでも「2009年も RE が発売されて驚いた」という記載がありましたから、 そのあたりから怪しかったのかもしれません。 マイナーチェンジも無く、およそ7年で終了したことになります。 とにかく特殊性の薄い入門用としては値段が高すぎる上に、 本格的なところも発展性も無いのが実態ですから、しかたありません。 さて、生産終了を前提に全頁の記述を見直すのも面倒だし、どうしたものか。 とりあえず少しずつ手直しにかかりましょう。 |
|
| 衰退期に入りネタも尽きましたので 2ちゃんねるから話題を拝借いたします | ||||
| 2ちゃんねるからの啓示 (その一・前半 〜BB高と登坂のお話) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
そう言われれば、確かにその通りだろうという気がします。
もし、Type-R にも当てはまるのであれば、 座面高を下げて相対的BB高が高くなった私のRよりも、 素のRの方が長い登りに有利ということになるはずですが・・・ 実際にはすべての走行シーンで、 bikeE に近づけた私のRの方が “比較的” な程度以上に楽に走れます。 (楽になるのではなく、より駆動力が得られると言った方が正確) 座面高以外に違いはありませんから、上の提言の証明にはぴったりなはずですが、 結果は見事に逆転しています。 Type-R においては、相対的BB高が高い方が登りでも有利 ! (同様に、bikeE も AT よりも CT の方が有利なのではないでしょうか?) |
|
|
これは「座面とBBとの落差は bikeE が限界」ということだと思います。 背もたれの立ち具合に応じた適正なBB高というか、座面との落差というものがあって、 bikeE はそこをきちんと押さえている。 腰の据わり具合と蹴り出す方向との兼ね合いが適正なのでしょう。 その落差を超えて “本当に蹴り込みが効かなくなった” のが Type-R の実態だと思います。 背もたれは bikeE 以上に起こすわけにもいかないでしょうから、 bikeE がリカンベントの限界、しきい値という気がします。 限界というのはバランス的に突き詰められた状態でもありますから、 そこに違いがあれば拙くなって当然ですね。 Type-R は残念なことにリカンベントの適正条件を満たしていないということになりますが、 乗り易さがあればそれがまかり通る、お気楽なユルいカテゴリーに救われて?います。 |
|
| 2ちゃんねるからの啓示 (その一・後半 〜呼吸のお話) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前半から話を繋いでしまえば、
上り坂では、BB高が低くシートバックが立っている方が呼吸に無理が無く長時間でも楽、となります。 なるほど確かにその通りだろう、という気がします。 BB高が高いほどシートバックが寝るのであれば、 前を見るためにあごを引く度合いが強まって、喉元も苦しくなりそうですし。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
上体を固定されたリカンベントでは、深い呼吸は確かにやり難い気がします。
平地でも、長く走っていると上体を動かせない状態に飽きがきて、 何となくうっとおしい気分になったりしますが、 本当は、背もたれのせいで胸郭が十分に広がらないのが原因ではないかと考えています。 肘が体に近く、脇も締まっていますし。 登り坂では、ハァハァゼェゼェやっていると車体がぶれ易くなりますから、 なるべくこじんまりと呼吸を整えて蛇行を抑えたいのですが、 酸素吸入に関して不利となれば、どうにもなりませんね。 こじんまりと収まっていられるのがリカンベントのお気楽さなんですが、 これを登り坂まで持ち込んでは、呼吸的にダメなわけです。 かといって元気に呼吸のできる体勢ではありません。 くどいようですが、リカンベントで呼吸を意識すると、 エコノミー席に座りっぱなしのような息苦しさに見舞われます。 棺桶に入っているのと似たようなものかもしれません。 身を起こして新鮮な空気を胸いっぱい吸い込みたいという欲求に囚われます。 呼吸に関しては、上体が立っていても不利なことに変わりはなさそうですね。 登りでも平地でも。 |
|||||||||||||
| 2ちゃんねるからの啓示 (その二 〜シートのお話など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
続いて、こちらも引用させていただきました。
>>471 やっぱりそうですよね。 何とかなるはずと思っても、すぐに欠陥確定ですよね〜。 斜め前方へ振り出しますから、どうにもなりません。 力学的に不利で、現実的に無理、機能的には欠陥です。 脚の着き方なんて、物理で習った力のベクトルを平行四辺形で分解するやつにぴったりはまりますね。 私はいつもそんな風に、先生が授業で使ってた棒みたいに長〜いスタンドを眺めていました。 懐かしいですねぇ、やっぱり勉強はしておくべきですね。 社会に出ても役に立ちました。 めでたし めでたし。 >>472 あらゆる意味でロードの対極にありますから、いろいろと見逃してもらえる部分も多くて、 組み合わせの相性としては、ある意味理想的かもしれません。 マッタリ 50km なら限度内ですが、お尻に良くありませんので散策程度に抑えるのが無難。 長距離には全く不向きなのは、皆さんが仰る通りです。 そこが惜しくて諦めきれない方も多くいらっしゃるはずですが。 >>473 アップライトと同じサドル調整のやり方が、どこまでリカンベントスタイルに通用するのか、 また、通用するようなものがリカンベントの範疇に入るのかということですね。 本家はリカンベントというワードを避けていますが、その範疇でしか話題にできないので、 愛を込めて?セミ・リカとか疑似リカンベントとか呼ばれているようなんですが、 勝手に引っ張りこまれて爪はじきにされて、踏んだり蹴ったりな “はみご” 状態だったりもします。 中途半端なところが嫌われちゃうわけですね。 ママチャリタイプのサドルなんて、リカンベント視点では時限爆弾でしかありませんし。 でも、もっとお手軽に、子供が公園で遊ぶような感覚で使えばドンピシャなもんだから、 これでイケるになったんでしょうねぇ〜。 遊んでるだけですから、生暖かく見守ってください。 >>475 快適距離が 10km というのは、かなりの苦言のようであって実のところ、 ある程度 Type-F に乗り慣れてくると、けっこう現実的な数値として了承できます。 言葉を変えれば、走り始めて身体がほぐれた時には、すでにお尻に警戒感が漂い始めている、 ということです。 肉体的な許容力や観察眼の個人差は大きいとは思いますが。 自分は快適に乗っているはずだという、観念というか信念のようなものが多少なりともありますから、 はっきりと痛みを認め始めた頃を境に、 それまでを快適、以降を不快とする切り分け方を無自覚にしがちです。 しかしお尻は徐々に痛めつけられていくのですから、 10km も走ればそれに気づいてしまう方もいらっしゃるでしょう。 Type-F の尻痛は蓄積されるのみで、途中で休憩してもチャラにはならない類のものです。 「快適」から「辛抱できる」に切り替わる距離がたったの 10km では悲しいものがありますが、 それを言い切った >>475 さんは、まさに真実を語っておられます。 ぜひ世を立て直す預言者となられますように。 >>480 乗車状態では、Type-F、Type-R、bikeE の背中の角度は似たようなものです。 にもかかわらず、Type-F の背もたれの取り付け角度がより垂直に近いのは事実です。 つまり背中と反りが合っていません。 出来る限り背もたれに荷重をかけて、お尻の負荷を減らしたいと切望する身にとっては、 かなりくそったれな現実なのですが、設計者は知らん顔です。 なのに文句の声はあまりに少ない。 (と言うより、情報発信が鎮静化した新型シートフレームでは聞いたことがありません) まさか、自信が持てずに後悔して人目を忍んであまり走れずにいる? まぁ、健康な精神をお持ちであれば、思ったようなものではなかった確率は高いかもしれません。 新型シートフレームって分かり難いですからね。 でも、きっと多くの方は何かに納得していらっしゃるんでしょう?? どうも Type-F には宗教のように、 現実の問題を直視させなくする中毒性が備わっているんじゃなかろうかという気がしてきますね。 こういうやつを選ぶという時点で、すでに現実に観念の世界を引っ張り込んでいますから、 迷いを捨てて彼岸の彼方から降臨させた以上は、あまり現世の俗な善悪判定基準に支配されたくない、 ということかもしれません。 乗り続けるにあたっては、その正当性を自分に納得させる理屈を頭の中で捏ねくり返しますから、 我に返って文句をつけるのは、もっと先の終末の時まで待たねばならないのでしょう。 Type-F 乗りに平安あれ。 まだこの世界は宗教を必要としています。 >>479、481 >>487 座り姿勢なのですからあまりに当たり前なお話と言えますが、 大雑把でありそうで基本は完成されている(と、私の眼には映っております)bikeE でもケツが痛い というのは初めて聞きました。 私が Type-R の比較対象として bikeE に興味を持った頃には、すでに bikeE社は倒産しており、 過去の遺物となった僅かな情報をかき集めるしかない状況でした。 旬な bikeE情報には無縁でしたので、こういった現実感のあるお話は参考になります。 また、壁に吊るされているのを一度見たきりの bikeE を、Type-R を批判的に克服するための 基準に据えている都合上、ご覧いただいている私のこのサイトにおける bikeE は、 どうしても理想像として立ち現われて来ざるを得ません。 それに現実的な肉付けをしてゆくには、こういった生の声に頼らざるをえないのですが、 残念なことに今や過去のものとなった bikeE も Type-R も、話題になることは稀です。 時すでに遅し。 |
|
| こちらも終了すべき時に 〜ありがとうございました。 やっぱりおかしいんだよなぁ、タル・エンタメ | ||||
|
このサイトもググれば引っ掛かるようになりましたし、幾らかの方にはご覧いただけたようです。
しかし、Type-F は “旧” モデルに則ったお話しでしかありません。 基本的な部分には現行モデルに通じるものがあると確信してはいるのですが、 やはり現行モデルは現行モデルオーナーの口から語られるべきものです。 また、Type-R はすでに生産終了した “過去” のものとなり、 このサイトに含まれた情報が、これから先に活かされる見込みも失せました。 このサイトは、Tartaruga Type-F という今ひとつよく分からんモノの情報提供が主眼です。 非常に(異常に?)個人的な目で見ればこんなものです、予備知識として活用して下さい、 のつもりなのです。 買った後でこんなはずではなかったのに、と嘆くのと、 その程度なら大丈夫、俺ならうまく切り抜ける、と腹を据えてかかるのとでは大違いですから。 本来であれば、本家サイトで多くのユーザーの工夫をかき集めて公開し、 その欠点と対策への道筋のあれこれを紹介すべきであった(過去形です)と考えています。 最初のオーナーズミーティング・TOMO(この時は参加したかったです)で、 そのような方向性を持てなかったのはなぜなんでしょう? 悩める者同士で安心しあってお終いではもったいないでしょうに。 やはり問題点にはできるだけ多くの人から、多くの意見を出していただいている方が、 (まとめたり結論付けたりする必要はありません) これから買おうとしている方だって手を出しやすいでしょう。 メーカーにも都合がありますから、ユーザーの現実対応の様を一々汲み取る必要は無く、 そこはすっぱり切り分けてしまって構わないのです。 「ユーザーの事はユーザーに任せる」でも構わないから、 そういった公開の場を設えるべきであったと思います。 とにかくユーザーが立ち往生しないよう、未完成なモノを支える場が必要だったのです。 それとは正反対の、TOMO 以降に強まった「タルタルーガ万歳」的な流れを見て、 ずっとそんな思いがくすぶり続けていたのですが、 「ユーザーの意見を重んじた改良」なるものが報じられるに至り、 「そんな訳ねぇだろ。 ユーザーの一人として言ってやる、俺はこう思うぞ」 、、、と余計な事に手をつけ始めてしまった訳です。 (注)TOMO=Tartaruga Owner's Meeting in Osaka です。 ユーザー主催の初集会で 2005/01 開催。 いつ頃このサイトを作ったのか覚えていないのですが、 検索エンジンに拾われるまでに一年ほどありましたから、 タルタルーガネタとしては更新期間が長い方だと思います。 しかし、今やすべては過去のモデルのお話となりました。 スイカの無いスイカ割りみたいに地面を叩き続けてもしかたありませんから、 切りのいいところで撤収する予定です。 ご無礼いたしました。 |
||
|
事の性質上、流行りのブログではやり難いのでホームページにしてみたのですが、
全くの知識無しのため、フリーソフトの簡単な所だけで工面しています。 見ていただいた方にはショボくて申し訳のない事だと思います。 ご容赦ください。 |
||
| 〜リンクを貼っていないリンク集〜 | ||||
|
◆自転車の保険に入ろう! http://jitensha-2.sakura.ne.jp/index.html(リンク切れ)
参考になります。 本当にありがとうございます。 私も JCB に入ることにいたしました。 ◆Ah My Tartaruga! http://www.remus.dti.ne.jp/~miwacchi/Tartaruga/index.html(リンク切れ) かつて閉鎖されたものの惜しむ声に応えて復活した記念碑的サイト。 F世代は私と同じ。 アイドラの自作、背もたれの改造等、当時の課題の記録に共感された方は多いはずです。 ◆でぃば〜じょん http://www.ne.jp/asahi/vow/nonsense/index.html ◆せんむちゃんの世界平和の道 http://www.senmuchan.mydns.jp/ おいしいとこだけ味わえる経済力に満ち溢れています。 が、ぱったり更新停止。 Ah My Tartaruga! と入れ違うように現れた、対極とも言えるサイト。 (2014/5リンク切れ確認) ◆心は前のめり日記。 (SweatBack Online) http://d.hatena.ne.jp/awborz/archive bikeE オーナーでもあり、Type-R との比較もちらほらと。 こちらも更新停止中。 ◆Tartaruga Entertainment Works http://www.tartaruga-ew.com リニューアル中と言いつつ、記念モデルの紹介だけは余念なし。 それ以外に目的は無さそうに見えたものの現在はそれなりに。 Type-R & RE の画像を載せるのであれば、生産終了モデルであることを明示すべき。 貴重な掲示板が無くなったのは惜しい。 いつの間に更新されたのか生産終了と記載されています(2015/05確認)。 ◆GREEN CYCLE STATION http://www.gcs-yokohama.com/ アドバイザーだそうです。 もちろん自転車のプロとしてだと思われますが。 責任を感じてか、かなりの肩入れ様です。 甲斐あってマエストロ最高位に。 ◆ミズタニ自転車(株) http://www.mizutanibike.co.jp/index.html 以前は取り扱い商品の50音インデックスがあってその中に「タルタルーガ」も入っていましたが、 今や完全消滅して無縁のサイトに。 振り返ればそういう時もあったというだけのお話。 Rの補修パーツは本家へ直メールすべし。 ◆CYCLETEC-IKD http://www.ikd21.co.jp/ikd/index.html DualDrive のユニットがラインナップされています。 これで万が一の時にも安心でしょう。 ◆Tartaruga-EW Yoshimatsuのブログ http://tartaruga.xsrv.jp/blog/ 2018/03〜 の吉松尚孝氏のブログ。 見つけたのは令和に改元された 2019/05。 やっぱりね、という裏取りができた点もありますが、情報源としては後出し過ぎるのと、 何故ここまでなのかについては得られるものが無いので、当サイトへの反映は見送る所存です。 |
|
| タルタルーガ FとR 目次 ・Top page |
| Type-F ハンドル周り ・シート ・パワーサポート ・ケーブル取り回し ・駆動系 ・その他 ・購入手引き |
| Type-R ハンドル周り ・シート ・ケーブル取り回し ・塗装品質 ・リアサス ・アイドラ ・どれほどbikeEか ・その他 |
| 雑記1 ・雑記2 Type-F 新型シートフレーム ・雑記3 Type-RE ・雑記4 チェーンオイル |
| 雑記5 XDS W5 ・雑記6 無印良品16型折りたたみ自転車 |