
 |
|
残念なことに Type-RE は見たことも乗ったこともありません。 よって雑記として扱っています。
まったく興味の対象外 だったので、まともに考えてみたのは今回が初めてなのですが、 かなり重要なモデルのようです。 |
|
| 熱のこもった RE の紹介 vs すっきりしない R の紹介 | ||||
|
|||||||||||||||||||
| 旧・本家サイトより (原文中の強調文字は青文字にて引用) | |||||||||||||||||||
|
・車名表記は一か所のみ “Type-R” と、ハイフンが入っておりますが、原文のままです。 ・「モーターアシスト」「モータアシスト」「モータ」も同様に統一性がありません。 ・理想的な重量配分の実現を理由に、さりげなく “独自の” という固別化が図られていますが、 「ミッドシップレイアウト」という表現は供給元のサンスター技研の受け売りのようです。 自動車の50対50といった前後輪の重量配分のお話ではなく、 荷重不足な前輪にユニットの重量が配分されることが、 理想的であり、独自発想なことだということです。 |
|
Type-R の紹介は、イメージの説明に終始しており、
具体的に自転車としてどうなのかには言及されていません。 日本古来の木造建築とリカンベントのフレームに共通イメージを認識せよ、 というショッキングなプレゼンを展開しただけで、 肝心の世界一乗りやすい理由を RE に持ち越してしまったからです。 おまけに開発趣旨を説明する最初のセンテンスは、 よく読むと何がどうなったのかはっきりしません。 「世界一乗りやすいリカンベントを目指したものです」とか、 「世界一乗りやすいリカンベントを設計しました」であれば文意明白ですが、 「開発を目指して設計」となれば、設計したものを使って別のものを開発するという、 二段構えの構想(=世界一と言えるカテゴリーを創設する)を意味します。 言葉が足りないのか余計なのかは別にして、 問題は、「世界一」を名乗りたいがRで先取りするわけにも行かないので、 「開発」という語を中途半端に割り込ませている点です。 bikeE のコピーであることを否定したいという意図は伝わりますが、文章としてはちょっと。 話を戻しましょう。 (設計したもの=Type-R)なのですから、おそらく次のような意味だと思われます。 |
|
|
「 世界一乗りやすいリカンベント 」 すなわち
「 高評価なbikeE 型の、世界初の電動アシスト付きリカンベント 」の開発 のために、まず Type-R を設計いたしました。 どのような設計かといえば “ Type-F 開発で確立した台形断面のフレームや角パイプのフロントフォーク等の オリジナリティを印象付けるノウハウをベースに bikeE を再構築し、 Tartaruga オリジナルモデルとして認知されることを目指しました。” |
|
|
続いて、そのオリジナル性を “独特な伝統建築フレーム” として説明しています。
自転車らしくない造形を自転車らしくないものに例えていますね。 お見事です ! |
|
|
原文の日本語はどうかという気がしますが、
このように隠し言葉である「bikeE」を補って解釈すれば、 事実無根の宣伝文句ではないことが見えてきます。 「世界初の電動アシスト付き」を「世界一乗りやすい」と表現して、 Rにも世界一をおすそ分け、ですね。 |
|
|
これは、
“ 既存の bikeE な段階を踏み台にして、世界初を「開発」した ” という宣言です。(というか、開発者という自負の表明) また、これらのモデル紹介文では、Type-RE のベースは Type-R で、 そのベースは Type-F という、順繰り構想になっています。 しかし、bikeE のスケルトンをベースに RE が企画され、そこからRが派生した、 というのが実態でしょうから、発売順に並べたものに意味を盛り付け過ぎています。 |
|
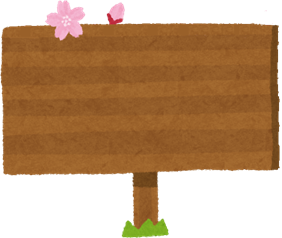
Type-R で証しせねばならないものは、
「bikeE ではないオリジナルデザイン」 ということらしいです。    |
|

日本発のリカンベントは 日本の伝統建築のはずでしたが、
電動パワーでターボパワーの The MIDSHIP になりました。 話の展開に付いていけませんが、栄光の世界初だそうです。 フェラーリも伝統がありますが・・・ それでイメージ結合しますかね? |
||
|
Ferrari Enzo (2002〜2004)
(https://www.sportscarmarket.com/profile/2003-ferrari-enzo;より) |
||
|
何となくリズムに乗せられてうっかり同時代の Enzo を引っ張り出してしまいましたが、
これ、ターボじゃありませんでした。 (´・ω・) スマソ でも、デザインはピニンファリーナの日本人デザイナーだそうです ! |
||
〜〜 余談ですが 〜〜 某ショップのWebサイトにて
 |
|
|
“伝統建築” というフレーズは、
上述の通り Type-R の紹介文で初めてそのフレーム構成を形容して用いられました。 その Type-R & RE も生産終了した以上は死語と化すかと思いきや、 台形断面のフレームパイプを示すものとして独り歩きを始めた模様です。 全モデルに採用されている “台形パイプ” がすなわち “日本の伝統建築” という、 さらなる論理の飛躍を遂げて Tartaruga の金科玉条と化したようです。 もう言葉遊びではなく、何でも飛び出すアリスの不思議の国。 |
|
|
現在はWebサイト更新に伴い該当する解説は消滅、刷新されています。
言葉を尽くして Tartaruga を語ろうという気持ちには共感できるものがあります。 が、そっちに流されて批判的な目を塞がれてしまうと進化は望めません。 事実、まともな進化などしていないじゃないですか。 Tartaruga に携わる自転車のプロショップなんだから、もっとしっかりしてください。 |
|
| RE が作りたかった ! | ||||
| 「自転車も実は最初 Type-RE までで止めようと思ってたんです。 自分で欲しいものは作ったから。」 | ||
| http://www.gcs-yokohama.com/tr_ny.htm より 〜リンク切れ | ||
|
欲しくて作ったのが RE で、商売上の必然が生んだのがRのようですね。
設計者の魂は RE にあります。 |
|
|
楽で面白い bikeE を電動アシスト化すればさらに楽しい乗り物ができあがる、
(あるいは、bikeE は電動アシスト化に適している) というのが真実な開発意図だったのではないでしょうか。 bikeE の使い道の一つの提案とも言える、デザイナーズ商品です。 |
|
| そうであるなら | |
|
Type-RE こそがベースモデルであり、
その Stripped Down バージョンが Type-R と思われます。 |
|
|
2003年の東京国際自転車展で Type-R が、 続いて翌年には Type-RE がお披露目となりました。
型式認定を受けてのデビュー間隔がたったの一年ですから、 先行発売の Type-R を電動アシスト化した派生バージョンではなく、 最初から電動アシスト車として開発されていたと考えるべきでしょう。 発売順は商売上の都合でしかありません。 「世界一乗りやすいリカンベントの開発」とは Type-R ではなく、RE を指すものとして理解できます。 |
|
| 〜〜 もしも、自社オリジナル企画では無いとしたら 〜〜 | |
| そもそも Type-R は、どう見ても bikeE の着せ替えバージョンです。 | |
|
エンターテイメントクリエイト集団を名乗る Tartaruga Entertainment Works が
そのような既存価値の複製でしかないものを自ら企画するとは思えません。 デザインスタジオとして依頼があれば話しは別かもしれませんが、、、 その場合であってもきっとエンターテイメント性を上乗せする提案をすることでしょう。 それが本領なのですから。 ((確かにそれも面白いけど、開発費はそっち持ちで))、、、 以前、某ショップのHPで 「巨費を投じて電動アシストバージョンまで開発した」 と称賛されていましたが、 何か関係あります? ところでミズタニ自転車と Type-R の関係ってどうなんですか? |
|
| RE は世界一乗りやすいリカンベント ??? | ||||
|
|||||||||||||||

|
|||||||||||||||
 |
||
 |
||
 |
||
|
(上) http://www.bs-asahi.co.jp/style/blog/2008/10/post-17.html より (中)旧・本家サイトより (下) http://www.macforest.com/cycling/other/040723_bdm/040723_bdm.html より |
||
|
一番上の画像では、メッシュシートのずれ具合の現実がよく分かります。
(上下が逆になっていますけど。 もっとも、その下の本家サイト画像までそのようでは困りますね) 素のRでも価格不相応と申しましたが、専用設計、専用品といった隙の無い出来栄えとは程遠い状態です。 本格的な何かではない証です。 電動アシストや、風力アシストができそうな立派なキャノピーよりも先に、 真面目に、取り組んでいただきたいものです。 |
|
| 重量増の恩恵 | |
| (その一) | |
|
Type-R よりも低重心で荷重の前後バランスが良いのですから、
ハンドルの安定感も高くきっと非常に乗りやすいと思います。 「アシストなしでもRと走りっぷりは変わらない ! 」というのが試乗報告の常ですが、 チェーンリングの歯数の違い(56T → 48T)を差し引いても、 このあたりが効いているのかもしれません。 感覚の落ち着かない短時間の印象ですから、ある程度割り引いて考える必要はあると思いますが。 (少なくとも違いを容易に感取できるほど煮詰まった設計水準ではなさそうですから、 乗り味から先は、行きずりな試乗ではかなりぼやけた領域のはずです) |
|
| (その二) | |
|
重い内装変速機が無くなった後輪は、サスペンションの動きも良くなっているでしょうし、
適度に荷重の加わった前輪は、細かな振動を押さえ込んでくれそうですから、 乗り心地も期待できます。 絶対的に重い以外はRよりも好ましい可能性が高く、 その重さも電力が供給される限りは全く問題にならないと思われますが、 そんな幸せが続くようにバッテリー残量に気を使い続けながら走るというのも、 かなりの頭脳労働で面倒そうですから、気ままに距離を伸ばすわけにはいかないんでしょうねぇ。 |
|
|
結果として
リカンベントの不安定な部分を排除する「ミッドシップレイアウト」にかなりの自信を持てたことは、 次作の Type-S を「SUV」などとクルマ用語で繋いでいることからも伺えます。 |
|
|
趣味の悪い言葉遊びに走っていますが、
クッソ重い電動アシスト車をクルマのイメージで救済するなんてなかなかですね。 |
|
| 弱点を克服して弱点を作る | |
|
航続距離はフルアシスト18km /平均30km(某有名店のWebサイトより)、車重6kg増の22.5kg。
全ては蓄電力頼みと化し、登り坂に弱いとされるリカンベントの弱点を克服して、 長距離に強いとされるリカンベントの長所を無くしました。 ですから、出来上がったものは「リカンベントらしからぬもの」になります。 自転車の楽しさの一つは、行動範囲が自ずと拡大してゆくことにあり、 リカンベントに対する期待も高まります。 しかし Type-RE にとっては楽なカタチがリカンベントなだけで、 遠くまで行くためのものではありません。 電動パワーに物言わせて何処でもより一層安楽に走れるようになったのに、 反則的ともいえる発進加速の快感も手に入れたのに、 アシスト距離というはっきりとした制限枠が出来上がってしまったのです。 力をつけたのに鎖につながれてしまいました。 6kgの重り+ユニットの引き摺り抵抗付きのトレーニングメニューをこなしながら距離を稼いでも、 そこに広がるのは精神修養の世界です。 リカンベントという「高効率」な形態のおかげで電力なしでも楽に走れる、 そんな旨い話などないのですから。 車重があっても速度維持が楽な車種はあるようですが、Type-RE はどうなんでしょうか? Type-R はだめなんですが、重量増を上手く使った Type-RE は、 ミラクルな走りを披露してくれるのでしょうか? |
|
| Qファクターの問題 | |
|
良く分からないのが、Qファクター。
唯一の情報源である諸元表が当てにならない上に、 試乗した方の感想も「そういえば大きかったような」といった具合ではどうにもならないのですが、 やはり電動アシストである以上はそれなりに大きいはずです。 Qファクターが大きいと、ペダリングの効率低下が懸念されます。 私のRのBB軸長は110mmですが、122.5mmを試用した際にはかなり違和感がありましたし、 アイドラとチェーンの絡み方も良くはなっていないようでした。 やはりQファクターは小さいに限ります。 電動アシストではハナから決まっていて受け入れる以外にないとはいえ、 中途半端なライディングフォームではカバーしきれないものが 時間とともに顕れてきそうな気がします。 また、おそらく、さらに気を萎えさせるのが、正面視の漕ぎ姿。 私は、しっかり締まったQファクターとハンドル幅でこそ、 何とか自転車らしい風情が保たれると診ているのですが、いかがでしょうか? 些かでも足元が広がってだらしなさが滲み出てしまうと、 Type-F の三輪車風情に転落する危険があります。 以上、うっかり既成概念に流されて物申しましたが、 マタマタ (´・ω・) スマソ 取っ替え引っ替えの試乗でも気になる事はなく、アシストなしでも違和感が無いのであれば、 程度以上に大きなQファクターは、RE の漕ぎに良い影響を与えるのかもしれません。 有名選手に倣ってQファクターを大きくしたところ、良い結果が得られたという事例もあるようです。 ただ、こちらはリカンベントでフォームが全く違いますし、 本当に気にならないのか、気が回らないだけなのか、の違いは気に留めておくべきでしょう。 |
|
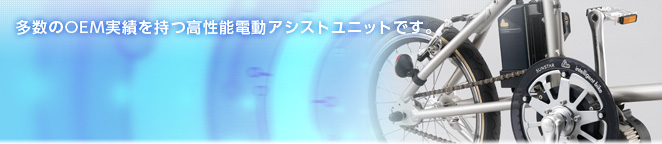 (サンスター技研より) (サンスター技研より)
|
|
| タルタルーガの血統 〜ただし雑種 | |
|
専用チューンといっても、
狙いどころをきちんと実現しているお買い物自転車のそれを凌ぐものではないのですから、 「電動 “パワー” アシスト付きリカンベント」などと、 何やらいいとこ取りしたような響きを持つカテゴリーを創設して誤魔化してはいけません。 後付け専用ユニットのために、自転車の方を専用開発してしまうというびっくりな発想はさておき、 カテゴリーとしては「企画物・コラボ製品」でしょうし、中身は「世界初」の組み合わせだけです。 「リカンベント」として Type-RE を見るのは厳しいものがあります。 天下の公道を遊び場と化すための道具として見た方が正しいという気がします。 楽に手に入る発進加速や登坂の快感が全てです。 労せず手に入れることの喜びがあればそれでよいのです。 電動アシストの役目を「生活の利便性」から、「遊びの優越感」に変えてしまったのですから、 とんでもないことをしてくれました。 人間が古いせいか、遊ぶことさえ楽させてやろうというのには抵抗を感じます。 現実的な実用性が希薄で、乗り回す所も無くて、 試乗みたいな運用を繰り返すことになりませんか? そんな憶測をブッ飛ばす面白さを電動アシストが実現しているとしても、 なぁ〜んだか世に馴染みにくいものを感じます、持たぬ者の偏見ですが。 《別頁》で遊具的な Type-F はトイザらスがお似合いだと揶揄しましたが、 それは自身の力が面白さに変わる、健康的な子供のような楽しさが実現されているからで、 対する RE は、楽な姿勢に電動アシストで楽を上乗せする快感、自身の力を出さない優越感ですから、 大人が公道で はしゃぐ、と言っても、向いている方向が逆です。 (Rはその中間で、お気楽さに はしゃぐ要素はあまり入っていません) この2台がその個性ではっきり自転車界を笑って(笑われて?)いるのに対し、 Type-R は RE から引き算した副産物です。 個性らしいものが何も残らなかったと惜しむべきか、そんな個性を落して難を逃れたと喜ぶべきか。 シリーズとしては初期にリアサスとキックスタンドの変更はありましたが、RE の型式認定が絡んでいるせいか、 それ以外は何らの変更も受けずに済んだことも幸いと言えるでしょう。 変更を重ねる Type-F を「原型が連続した流れの中で発展してゆく」と見るのは、現状肯定のための進化妄想です。 何も起こさないことが保全につながったのがRです。 |
|
|
|
|
|||
| 電動アシストってホントはどうなの? 「 電動アシスト自転車 まとめ @Wiki-小径車タイプ(スポーツ)」より | ||||
|
|||||||||||||||
|
Type-RE では身重すぎということですかぁ。 だとすると、禁断の組み合わせですよねぇ。
22.5kgの車体に3.4Ahでは、短距離お使い限定に毛の生えた程度です。 電池容量が小さいという問題は共通していますから、使い方も同じになります。 が、こちらは軽量さでアシストを補うのは無理。 だから、十分なパワフルさも無理。 (というか、補う必要のあるアシストユニットというのでは話が逆さまでしょう) これだとターボモードでの発進(のレスポンス)が快感レベルというのが精いっぱいそうですね。 |
|
|
「登り坂に弱いとされるリカンベントの弱点」を、
パワーを出し渋る登り坂に弱いユニットで、 どの程度克服しているのか気になります。 |
|
|
2時間の充電で、アシスト感のある走りが2時間(=30km)は楽しめるようですから、
バッテリーの活きが良いうちは、充電効率に不満を感じることはなさそうですね。 「あったらあったで面白い」、「ちょっと試しで遊んでみる」には十分なだけのアシストは 実現しているはずですが、何かを本格的に考えたり突き詰めたりしたものではありませんよねぇ〜。 |
|
|
閃いたら与しやすそうなあれとこれをくっつけて、
一番乗りを目指して電動アシスト神話の世界へレッツゴーです。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
RE は2モードで、航続距離はフルアシスト18km /平均30kmだそうです。
これは上の表では5Ah相当に見えますが、RE の電池容量は3.4Ahしかありませんから、 かなりな節電チューニングを施して航続距離を稼ぎ出していることになります。 (最初の一踏みを除けば、チェーンの取り回し抵抗等をキャンセルする程度に働くだけとか) そこまで絞れば何のために電動アシストが付いているのか怪しくなってきますが、 アイドラの耐久性はさらに怪しいので、実情に即した設定と言えるでしょう。 あるいは、 |
|
|
元からペダリング効率が悪くトルクが掛からない ので、
アシスト量が少なくて済むのかもしれません。 |
|
|
だったら、「アシスト無しでも走りっぷりが変わらない」でしょうね。 話は合います。 (これ、誉め言葉にはなりませんよねぇ) 《→トルク不足について》 |
|
| 結果としては “専用チューン” と呼ぶにふさわしい奇跡的な現象と言えると思います。 | |
|
||||||||
|
そもそも一回の走行分にも満たないような容量の足りない電池が年々劣化し、
ちょっとした悪条件(ともすれば重なるのが悪条件)で航続距離がガタ落ちし、 管理するには 精神的な不便を感じる度合い が大きい、 ということであれば、電動アシストを選ぶ楽しさなど何処にも無さそうに思えます。 買った後はただひたすらに面倒臭そう。 |
|
|
自分の使い方に合っているのか見当がつかなければ、おいそれと手は出せませんね。
でも、電動アシストの付いたリカンベントの使い方など買ってみないと分からないでしょう。 買ってしまった自分のフロンティア精神を自慢しましょう。 こういった魔が差したような、見切り発車的決断を伴う購入感は、Type-F、Type-R に共通するものです。 Type-S は不明です。 こちらは素性が Pacific の REACH という保証?が効けばよろしいのですが、 Tartaruga というブランドに対する躊躇という点では同じものがあるかもしれません。 サンスター技研は 2017年に電動アシストから撤退しており、バッテリー供給も途絶えました。 Type-RE は生産終了後の余命を保つことは不可となり、完全消滅に向かってまっしぐらです。 追記) 2018年に株式会社陽報がサンスター技研の自転車「電動アシストユニット事業」を事業譲受したそうです。 |
|
| R と RE の違い | ||||
|
電動パワーに何とかしてもらうのか、
変速パターン数を頼りに自分で何とかやりくりするのか、 の違いですね。 努力は航続距離に大きく反映されます。 R は駆動系が 18in. の Type-F に準じたままの 20in. 化なので、 24通りのギアの組み合わせの内、 (内装100%)×(11T、12T) (内装136%)×(11T〜16T)の6パターンは高速過ぎて現実的ではありませんが、 それ以外にまだ18パターンも残っていますから、ユーザーが何とかすれば立派に走れます。 他力本願には制限があるし、自力も面倒そうだし、、、これって《ママチャリ》でしたっけ? 、、、、他を当たってみてはいかがでしょうか? |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(注)
●本家サイトには Type-R/RE の価格の記載はありませんでした。 ●RE のギアクランクは見た目通りに別物、サンスター技研のアッセンブル品でしょう。 ●BBセットも、RE はサンスター技研のアッセンブル品でしょう。 ●チェーンのリンク数が同じというのはありえますが、チェーンリングの歯数差とRDのケージサイズの違いを考えると (SORA はショートケージ、SRAM はロングケージ相当?)、ちょっと怪しいです。 ●シマノのグリップシフターは正しくは「レボシフトレバー」です。 |
|
| タルタルーガ FとR 目次 ・Top page |
| Type-F ハンドル周り ・シート ・パワーサポート ・ケーブル取り回し ・駆動系 ・その他 ・購入手引き |
| Type-R ハンドル周り ・シート ・ケーブル取り回し ・塗装品質 ・リアサス ・アイドラ ・どれほどbikeEか ・その他 |
| 雑記1 ・雑記2 Type-F 新型シートフレーム ・雑記3 Type-RE ・雑記4 チェーンオイル |
| 雑記5 XDS W5 ・雑記6 無印良品16型折りたたみ自転車 |