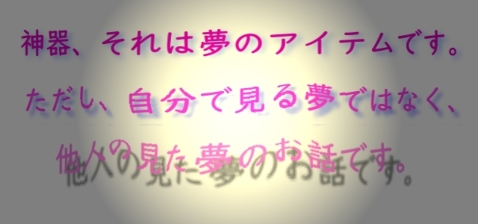| Date |
Odometer |
Contents |
| 2006/10/28 |
12238 |
(Type-F より積算距離引継ぎ) |
| 11/12 |
12310 |
ハンドルポジションチェンジャー装着 (Type-Fより引継ぎ)
クランクセット交換 SORA (165mm) + シュパーブブロ 52T (Type-Fより引継ぎ)
ペダル交換 PD-M520 (SPD) (Type-Fより引継ぎ)
チェーン交換 CN-HG73 (9Speeds) 212Links
チェーンチューブ撤去 |
| 11/19 |
12392 |
タイヤ交換 F=MARATHON 1.75×16 (BIG APPLE 入手困難のため) R=BIG APPLE |
| 11/26 |
12425 |
チェーンリング交換 シュパーブプロ 43T
チェーン駒詰め 208Links |
| 12/02 |
12485 |
シフター交換 SHIMANO SL-M740 (XT) (Type-Fより引継ぎ)+SRAM Attack halfpipe
ディレーラー交換 SHIMANO RD-M760 (XT) (Type-Fより引継ぎ)
ブレーキレバー交換 BL-M511-L (Deore) (Type-Fより引継ぎ)
Rブレーキ交換 Avid SD3 シュー交換 CoolStop (前後共) (Type-Fより引継ぎ)
グリップ交換 Answer Aggressor (Type-Fより引継ぎ)
全ケーブル交換・取り回し変更 |
| 12/16 |
(12600) |
ハンドルバーカット 両端各20mm |
| 2007/02/04 |
13077 |
BB交換 68-116 (Tange LN7922) (オリジナルと同じ) |
| 02/11 |
13214 |
BB交換 68-113 (Tange LN7922) (チェーンライン調整) |
| 03/03 |
13309 |
BB交換 68-110 (Tange LN7922) (チェーンライン調整) |
| 03/10 |
13390 |
サス交換 KIND SHOCK KS-562
チェーン交換 CN-HG73 206Links |
| 03/18 |
13439 |
BB交換 68-118 (Tange LN7922) (Type-Fより引継ぎ) (アイドラ負荷調査)
BB交換 68-122.5 (Tange LN7922) (アイドラ負荷調査) |
| 04/08 |
13538 |
BB交換 68-110 (Tange LN7922) (再使用) |
| 05/05 |
13957 |
Rタイヤ交換 BIG APPLE |
| 09/01 |
15150 |
サイコン交換 |
| 11/17 |
15989 |
ハンドルバー交換 グランジDHストレートハンドルバー (より角度の付いたもの) |
| 11/18 |
16025 |
ハンドルバー交換 オリジナルに戻す |
| 12/31 |
16382 |
Rブレーキシュー交換 XTR (Yahoo!オークションにて割安) |
| 2008/01/06 |
16529 |
Rブレーキパッド交換 S70C (ドライ用) |
| 02/03 |
16687 |
Fタイヤ交換 BIG APPLE |
| 05/19 |
17798 |
Rタイヤ交換 BIG APPLE |
| 08/10 |
18389 |
チェーン交換 CN-HG73
アイドラ裏返し |
| 10/12 |
18924 |
サス交換 オリジナル(RST22)に戻す (KIND SHOCK KS-562故障のため)
タイヤ空気圧変更 最大圧での使用を中止 |
| 11/15 |
19181 |
サス交換 KIND SHOCK KS-582 |
| 2009/09/21 |
20911 |
Rタイヤ交換 BIG APPLE |
| 11/21 |
21379 |
Fハブ グリスアップ (RESPO使用) |
| 11/23 |
21405 |
サス取付け穴追加 (取付け長150mm用) |
| 12/30 |
21812 |
アイドラ交換 (補修パーツ・新品に) |
| 2010/07/25 |
(22470) |
サス取付け穴追加 |
| 09/12 |
22787 |
アイドラ交換 (元のオリジナルパーツに・再使用) |
| 09/18 |
22821 |
チェーン駒詰め 204Links |
| 10/08 |
22978 |
チェーン、スプロケ、チェーンリング交換 |
| 10/16 |
23072 |
グリップシフター交換 SRAM X9
グリップ交換 XCスリムグリップ
Fハブ グリスアップ 玉押し、ベアリング交換
アイドラ交換 (交換前の補修パーツに・再使用) |
| 2011/04/10 |
23646 |
Rハブ 玉押し調整 |
| 05/02 |
23753 |
Rハブ グリスアップ |
| 2012/05/26 |
24531 |
グリップ交換 エルゴタイプ |
| 2016/04/10 |
27886 |
F/R タイヤ&チューブ交換 BIG APPLE |